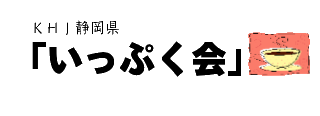活動内容
いっぷく会便り 2015年12月号
平成27年12月1日 発行
NPO法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会 静岡県「いっぷく会」
会長 上杉 博美
日時 |
平成27年11月8日(日)
|
|---|---|
テーマ |
「一歩進めたコミュニケーション」
|
講師 |
NPO法人フレンドスペース カウンセラー 菊池 恒先生
|
会場 |
静岡市番町市民活動センター 2F・大会議室
|
PDFファイル201512.pdf![]()
全国組織の名称が変更されました
平成27年12月1日より全国組織の名称が新しくなりました。
旧)NPO法人 全国引きこもりKHJ親の会(家族会連合会)
新)NPO法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会
『親の会から「家族会」へ、今後は広く、親、本人、きょうだい、支援者含め、全国組織を有する唯一の
ひきこもり当事者団体として、当事者本人の社会参加が少しでも進むよう活動してまいりたいと存じま
す。』とコメントしています。
11月例会のご報告
11月の例会は、11月8日(日) 静岡市番町市民活動センターで開催しました。
◆準備会 10時~
上杉会長など14名参加がありました。
まず「いっぷく会便り11月号」「12月会員交流会案内」「忘年会案内」を入れて、参加者への配布、
欠席者、関係機関への郵送作業を行いました。そして、いくつかの報告事項、協議事項を話し合い、
あとは昼食をはさんで楽しい歓談の時間を過ごしました。場所も毎月の例会場と同じですので、親の
居場所でもあります。弁当持参ですが、例会に少し早めにお出かけいただく感じで出かけて下さい。
とても楽しい時間です。是非とも遠慮なくお出かけ下さい。
◆例会 13時15分~16時40分 参加者27名(初参加0名、当事者1名含む)
◇会長挨拶と活動報告
ご出席のお礼を申し上げます。先頃長野に紅葉見物に出かけてきました。自然を満喫し、親も適度に
ストレスを解消しながら取組む必要があると感じました。暮れになるとお酒の機会も多くなりますが、
体調には十分に気をつけながらやって下さい。本日も有意義な学習をいたしましょう。
活動報告は、11月の個別相談会、多少の空きがある旨案内。12月会員交流会、忘年会の案内。
バザーへのご協力をお願いしたい。1月31日に講演会を予定しているなどの案内をしました。
◇連続学習会 13時30分~16時40分
テーマ「一歩進めたコミュニケーション」
講師 NPO法人フレンドスペース カウンセラー
(人間関係と心の相談舎)菊池 恒先生
・まずはじめ、音楽を聞いて気持ちをリセット。心を落着かせる時間があると良いですね。
あるドラマを見て、「伝えるもの」と「伝わるもの」は別であること(違う)そして「自分が気に
なっていること」は「相手も気になっていることがある」可能性がある。ということを学び本題に
入った。
1、コミュニケーションの基本=コツ
①ゆっくりと、落ち着いて(話す速さ、間合い、話の展開・・)
話を聴くなら、焦って喋らない。話をしたいなら、焦って喋らないことが大切です。
②スキをつくる(受け止め過ぎず、流し過ぎず)相手から話しやすい状況をつくる。
③流れをつくる(接続詞を駆使する)
否定形ではなく、関心を注ぐ接続詞は「あ~そう」「なるほどね」 これを大事にしたいですね。
人間には「恒常性」と言うのがあり、今の状態を保とうとする機能のことで、急激な変化は相手
が拒否することが多い。親も子も今までのパターンをもっているので変えるのはひと苦労です。
2、コミュニケーション・ステージ
①ステージによる声かけ・質の違い
(6)完全断絶 ・・・会話・伝達・遭遇 が一切なし。
(5)稀接触 ・・・ニアミス・暗号的示唆(音とか、形跡で感ずる)
(4)交流判断 ・・・警戒と手探り(少し声かけすると少し反応があったり・・)
(3)日常的交流 ・・・核心には触れない・雪解け
(2)一方的感情放出・・・本音・感情の伝達(親は聞くことに徹するのがベストです)
(1)準緊張状態 ・・・少し遠慮とギクシャク
(0)自然体 ・・・相互に楽な関係
②コミュニケーションスタイルは徐々に変化を、距離を近づけるのはゆっくり。
急激な変化はお互いにストレスになります。
③要求や心情は相手本位で。本音がどこにあるのか近づいてみる。
親の要求と子の要求。Win—Winの関係になるように。
これらを纏めると、子どもに対して「変化の距離は遠くからやって」「関心は近くにもってくださ
い」ということでしょうか。
3、一歩進めるための具体的方法
①(初級)トランシーバー式会話方法=「どうぞ」がすべて
これは一方通行の入れ替わりの繰返しです。同時に双方向からの会話はできません。
簡潔に、伝えたい内容を如何に分かるように話して「どうぞ」で 相手の話を聞くということ
です。
この会話を、二人組で体験した。「きちんと聞いて、きちんと話す」 普段出来ていないこと
ですね。
②(中級)選択式問いかけ方法=「その他」の可能性
子どもが何も話さない時・・・可能な限りの選択肢を考えてみましょう。
例えばAとBがあって、それを選ぶときの選び方は数学的には4つあります。(A、B、AもB
も、どちらも選ばない) でも現実はそんなきちんとはいきません。
だんまりの状態で、何故喋らないか? ①喋りたくない ②喋りたいけど喋れない ③喋りた
いけど喋ってはいけない ④言葉にできない。などが考えられるが、最後につけて欲しいのは
「その他」これらに入らない要因がある可能性があるのです。
③(上級)きっかけ&タイミングを自分から作る方法
きっかけやタイミングは作らないとできません。こちらから作るということです。
④(上級)言語的・印象的変換問いかけ方法
相手が言ってきた言葉、状態をこちらが受取りやすい言葉に変換しても良いかと問いかけなが
らやる。 例えば、「苦しい」は「つらい」と変換しても良いのか?
③④については今回 詳しくは省略した。
4、その他の要素
①事実判断と価値判断
「事実判断」は、誰が見ても変わらないもの。「価値判断」は、その時により、状況により変わ
ってゆくものです。日常はこれらをぐちゃぐちゃに使っていることが多いです。
でも、きちんとわきまえて考えないといけませんね。コミュニケーションの行き違いになります。
②ハインリッヒの法則(300:29:1)
産業界で使われている法則です。大事故が起こるまでには「300件のヒヤリ、ハッとした事故が
起き」「29件の中規模の事故が起き」そして「1件の致命的な大事故に至る」というものです。
コミュニケーションにおいても、ある日プチンと切れて大暴れするようだったら、その前に親の
気がつかない300件の前兆などがあったということではないでしょうか。普段からのコミュニケ
ーションの中で、観察と対応も必要ですね。
③積極的待機(精神的スクランブル)
積極的に待つということです。つまり飛び込んできたら、即座に立てるような状況を考えておく
こと。
④不思議なコミュニケーションの話(アフリカの母と赤子)
アフリカの未開拓部落でのリポートで、1か月の赤ちゃんに母親が「あっち」と言うと、その方
向で便、小便などの用をして戻ってくる。赤ちゃんは何で分かるのでしょうか?
コミュニケーションの不思議なところですね。
・コミュニケーションは生ものです、絶対的な正解というものはありません。これらのことをわきま
えて子どもに接するということですね。 子どもは何で満足するのでしょうか? 「どうしたの?」
と、関心をもってくれる、理解しようとしてくれるだけで良いのです。とまとめて頂きました。
・その後、質疑応答の時間を頂いて、多数の質問に丁寧にお答えいただきました。
ありがとうございました。
◇グループでの話し合い。
時間がなくなってしまいましたので本日は中止しました。
1月例会のお知らせ
日時 : 平成28年 1月10日(日) 13:15 ~ 17:00
会場 :静岡県男女共同参画センター「あざれあ」4階 第2会議室
<連続学習会テーマ>
『親の価値観・生き方と
本人の価値観・内面・行動のギャップ』
(講師)一般社団法人SCSカウンセリング研究所
カウンセラー 三橋 由江 先生
※ 講師の都合により、11月に予定したものが1月に変更されましたのでご了承下さい。
(参加費)会員1名1500円(ご夫婦2000円) 当事者無料 非会員1名2000円
初めて参加の方は初回のみ無料です。ご参加をお待ちしています
参加申し込みは必要ありません。当日会場までお越しください。
「個別相談会」のお知らせ
日時 : 平成28年 1月23日(土)、24日(日)
場所 : 静岡市番町市民活動センター 2F 小会議室
23日(土) 9:30 ~ 16:30
24日(日) 9:30 ~ 17:30
(カウンセラー) NPO法人フレンドスペース 菊池 恒 先生
相談時間 1家族=50分 80分 110分の各コース(会員限定・有料)
お問い合わせ・お申込みは TEL・FAX 054-245-0766(中津川)まで
講演会の開催を予定しています!
日 時 平成28年1月31日(日) 14:00より16:00頃
会 場 静岡市番町市民活動センター 2階 大会議室
演 題 「 ひきこもりのことで悩んでいませんか! 」
~静岡県ひきこもり支援センターからの報告~
講 師 静岡県精神保健福祉センター
(静岡県ひきこもり支援センター) 臨床心理士 菅沼 文 氏
参加費 無料
今回は少し視点を変えて、せっかくあるひとつの行政支援機関をどのように利用から
したらよいか、そのシステム、あわせてセンターから見たひきこもりの医学的、心理
学的概念と実態、およびそこから得られる対応方法を学びとる講座です。
詳しくはチラシを御覧ください。
会長コラム
12月に入って何かと慌ただしい日々になってきました。忘年会のシーズンになり、お身体をいたわっ
て、お酒は控えめにして下さいね。
当事者のこだわりのある、自分本意の考えを分かってやれないサポートではいけないのかと思っていま
す。当事者が成長したい、評価して欲しい、支えて欲しい、手助けして欲しいなど。色々な気持ちを内
に秘めて、日々複雑な気持ちで毎日、悶々としているのだと思っています。
ピアサポーターも困難な要求も理解しながら支えられるように知識を増やして当事者と信頼関係を作
って前進していきたいものです。
身体が元気でないと子供を支えられません。ストレス無いように元気にして下さい。
初めてご参加の方は月例会会場で入会手続きができます。
年会費6000円 月例会参加費お一人1500円(ご夫婦参加2000円)
その他、いっぷく会へのお問い合わせは事務局までお願いします。
事務局 電話・FAX 054-245-0766 担当 中津川
連続学習会は「赤い羽根共同募金」の助成を受けて運営されています。