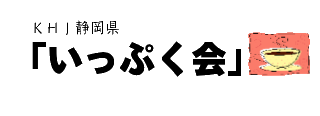活動内容
いっぷく会便り 2021年1月号
令和3年1月1日 発行
NPO法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会 静岡県「いっぷく会」
会長 中村 彰男
|
日時
|
2020年12月13日(日)
|
|---|---|
|
テーマ
|
「事件に学ぶひきこもり対応 ~経験者・相談員の立場から~」
|
|
講師
|
ヒューマン・スタジオ 代表 丸山 康彦氏
|
|
会場
|
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
|
PDFファイル202101.pdf![]()
12月例会のご報告
12月例会は、12月13日(日)静岡県男女共同参画センター「あざれあ」4F研修室で開催しました。
◇準備会 10時~
16名の参加をいただきました。まず「いっぷく会便り12月号」「たびだち秋季号」「1~3月学習会案内」「1月個別相談会案内」「東部地区会のお誘い」「KHJ本部アンケート」「関係機関に対しての学習会お誘い文書」を入れて出席者への配布、欠席者・関係機関への郵送作業を行いました。
そしていくつかの報告事項、打ち合わせをして、各種情報などについて話し合いました。そして最近は、ミニ学習会も行っています。
あとは昼食をとりながら楽しい歓談の時間を過ごしました。今日は年1回、昼食に親子丼弁当を皆で頂きました。どなたでも例会に少し早めに出かける感じで参加してみて下さい。都合のつく時間からでも構いませんので、是非とも楽しいゆっくりとした時間を共有しましょう。
◆例会 13時15分~16時30分 参加者28家族31名でした
◇連続学習会
テーマ「 事件に学ぶひきこもり対応 ~ 経験者・相談員の立場から ~ 」
講師 ヒューマン・スタジオ 代表 丸山 康彦氏
いっぷく会には、昨年5月に次いで2回目となります。昨年の川崎、練馬での2大事件をきっかけにひきこもり問題が大きく動き出しています。今回は、「事件に学ぶひきこもり対応」についてお話しします。
1.ひきこもり本人をどう見ていますか
①本人への見方と対応のイメージ
これは大変重要なことで、3通りの見方があります。そして、「否定的」に見るのか「肯定的」に見るのかによって対応も大きく変わってきます。
・否定的な見方
-「精神病理」や「ひ弱」だからだと“異常”とみなし治療が必要だと考える
-「怠け」や「わがまま」だからだと“悪行”とみなし矯正が必要だと考える
つまり、ひきこもりは悪い状態であるから、一日も早く本来の姿に戻らせなければとの発想となり、ひきこもり状態の人を“病人・犯罪者”であるかのように対応することとなります。
・肯定的な見方
-「生きざま」である。生き方は選べますが、選ばざるを得なかった道がひきこもりであって、正に“困難局面”であると言えます。
対応は、早く何とかと言うことではなくて、配慮(出来ていることはそのままやらせる、危険なことや出来ないことは代わりにやってあげる)して、そのまま歩かせることです。妊婦への接し方と同様です。すると、人それぞれ歩くコースが変わってきて、生き方を考え出し、それぞれの目標が生まれてくるものです。
②「社会に出られない」という<今の本人>
を直視するか、「社会に出るのが当然」という<あるべき人間像>を前提にそのレベルから逆算して本人を見下ろすか。
「直視」と「逆算」の違いです。
-「直視」は肯定することであり、
・本人の現状を認め、できていることを数える
・本人の心理に合った対応を考える
・目線を本人と同じ高さに合わせ、フラットに見る
これによって、本人の意思に対して、下記の対応が出来るようになるのです。
・軽く扱わない(認める)
・きちんと受け止める
・一般の人の場合と同様に扱う
-「逆算」は否定することであり、
・一般の人に比べ“どれだけ未熟で何が足りないか”を考え、前提とするレベルまで引き上げようとする
・良し悪し、優劣、精神的強弱といった縦軸で見てしまう
これによって、本人の意思に対しては、不当なことだと捉え下記の対応となってしまうのです。
・軽く扱う(挫こうとする)
・相手にしない
・一般の人と違う扱いをする
2.ひきこもり本人とどう生きていますか
①教育家族から生活家族へ:家族生活をやり直す
・家族の一員として接する
教育家族(家族の存在意義が子どもの教育にある)が主流となった時代において、社会から離脱したわが子を「仕事をしていない誰々」と見るのではなく、今まで通りの「わが子/きょうだいの誰々」として見て下さい。生活家族(生活共同体)として生活そのものに焦点を当て直すことが大切です。
家族からどう見られているか、本人にとっては非常に敏感になるもので、ましてや家族の一員として認められないと、生きるモチベーションが下がってしまうのです。
・教育意識から個別意識へ
教育は評価を伴っているものであり、その評価がその人の人物評価に直結しています。また、審判的態度(善し悪し、優劣、強弱で見る)、正論、べき論も避けて下さい。無評価・非審判的態度で接するようにして下さい。
教育意識は、定められた目標・理想に向かって引き上げて行くものであり、あるべき人物像から逆算して本人を見ることになります。正に教育は逆算の営みだと言えます。
評価の軸を突破らって、一人ひとり個別意識(個々に見ていく)で、現状の本人を直視することが大切です。
・支援思考から生活思考へ
どうにかしなきゃ、なんとかしなきゃではなくて、わが子の生活に寄り添うようにして下さい。
「救ってあげる」「向き合う」から「仲良く暮らす」「横並び」へ
「ひきこもり生活を終わらせる」から「ひきこもり生活の質を高める」へ
「指導する」「技術で何とか」から「家族の幸せを追求する」「皮膚感覚による判断」へ
②プロセスづくりの重要性:歳月を味方につける(日にち薬を服用する)
家族・支援者は、ひきこもり状態の長期化を防ごうとしてどうしても焦ってしまうものです。
長期化への対応として、
・会話の地層
歳月につれてどう対応を変えて行けばいいのかが分かっていれば対応が出来ます。
まずは、“日常会話”を定着させ、“深い話”へ、そして“本題”へと順に積み重ねていくのです。
年月につれて、会話の内容(下記)と量を増やしていくのです。
- 日常会話:挨拶・雑談・用件の話 「報・連・相(報告・連絡・相談)」から始める
- 深い話 :社会・人生談義、互いの打ち明け話
- 本題 :進路をどうするかor現状をどう受け入れるか
・判断と自然
一般的な家族は皮膚感覚で“自然”に会話をしていますが、ひきこもりの子どもに対しては言っていいのか悪いのか“判断”しながら会話を進めることになります。この“判断”と“自然”の比率が、本人の変化によって“判断”<“自然”へと変わっていくものです。
3.ふたつの事件から何を思いますか
①川崎(登戸)児童等殺傷自殺事件 【相談員の研修不足】
・犯人:ネグレクト的に育てられた後、叔父・叔母・義兄弟と暮らす
・相談員:叔父・叔母からの「会話ができない」という相談に対して手紙を書くように助言した
しかしながら手紙の内容は「お前はひきこもりだから自立しなさい」だった
そのため手紙は破り捨てられ、相談は中断した
・私が相談員だったら
手紙を書くよう助言するなら、手紙の中身を「会話の地層」にもとづいて書くように助言する
まずは日常会話、定着したら深い話へと
それがいきなり、本題の「お前はひきこもりだから自立しなさい」では、当然の結果を生じてしまう
②練馬元事務次官息子殺害事件 【息子を直視できなかった両親】
・犯人:エリートの父は息子に対応(コミケに同伴、アパート賃借)したが、暴力を振るわれ川崎事件を想起した
・被害者:父を畏敬・母を軽蔑(とりわけ母に暴力)、独り暮らしに失敗、実家に帰り父に暴力
・類似の事件:開成高校生殺害事件、浦和高校教師息子殺害事件、東京湯島・金属バット殺害事件との共通点に母親の教育熱心があげられる
・私が両親だったら
本人への見方を逆算から直視に変えたうえ、生活思考で接する
暴力への対処を学ぶ[姿勢:人間対人間としての関係(境界線・距離感)、方法:ひと晩外泊して翌日帰宅するなど]
今日は、色々な実例を踏まえ学習させていただきました。質疑応答を含め大変ありがとうございました。
2月例会のお知らせ
日時 :令和3年2月14日(日) 13:15 ~ 16:30 (受付 13:00~)
会場 :静岡市番町市民活動センター 2F 大会議室
連続学習会テーマ:『 ひきこもり回復 トラブルにこそヒントがある 生かせるかは親次第 』
講師:SCSカウンセリング研究所 副代表 臨床心理士 桝田 智彦氏
<参加費>1家族 ワンコイン! 500円、初参加の方、当事者の方 無料
尚、当日10時より同場所で準備会を行っていますので。お気軽に是非ご参加下さい。
◆新型コロナの状況により、変更せざるを得ない場合がありますのでお含みおき下さい。
受付当番 : ■富士市以東 □静岡市駿河区、清水区 □静岡市葵区 □藤枝・焼津市以西
■の地区の方よろしくお願いします。
「個別相談会」のお知らせ
日時:令和 3年 1月22日(金)9:30 ~21:00 小会議室
23日(土)9:30 ~21:00 中会議室
24日(日)9:30 ~18:00 小会議室
場所:静岡市番町市民活動センター
(カウンセラー)「人間関係と心の相談舎」代表 菊池 恒 先生
相談時間 1家族=50分 80分 110分の各コース(会員限定・有料)
お申込み・お問い合わせは TEL・FAX 054-245-0766(中津川)まで
「いっぷくサロン」 気軽にお出かけください(当番がいます)
毎週火・木曜日 午後1時~4時(但し、祝日、年末年始は除く)
静岡市葵区一番町50番地 静岡市番町市民活動センター2F KHJ静岡県いっぷく会 事務所内
尚、お出かけにあたりましては「マスクの着用」などお忘れなくお願いします。
《会長コラム》
1年も続くコロナ禍、まだ当分収まりそうにもありません。後世の歴史家はこの状況をどのように記すのであろうか。最も気になるのは人心、特に子供たちに及ぼす影響であります。あらゆる分野で既存の常識が音を立てて崩れ去り、決して元には戻らないことだけは確かなようであります。私たち自身の日常についても、改めて問い直しを迫られている事項が多いことに気づかされます。新年にあたりできるところから始めようと素直に考えております。
初めてご参加の方、初回は体験として無料です。その後よろしければいつでも入会手続き
ができます。年会費は6000円で、出席した時には参加費のご負担をお願いします。
その他、いっぷく会へのお問い合わせは事務局までお願いします。
事務局 電話・FAX 054-245-0766 担当 中津川
E-mail:ippuku-kai@outlook.jp
本会の活動は「赤い羽根共同募金」の助成を受けて運営しています。