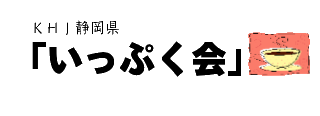活動内容
いっぷく会便り 2017年5月号
平成29年5月1日 発行
NPO法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会 静岡県「いっぷく会」
会長 中村 彰男
|
日時
|
平成29年4月9日(日)
|
|---|---|
|
テーマ
|
「ひきこもり・親の取り組みが必要」
|
|
講師
|
SCSカウンセリング研究所 代表 桝田 宏子先生
|
|
会場
|
静岡市番町市民活動センター
|
PDFファイル201705.pdf![]()
「平成28年度いっぷく会総会」が開催されました
4月の例会の中で、平成28年度総会が開催されました。
総会では、まず「平成28年度の活動報告、決算報告」が行われ承認されました。
続いて役員の選出が行われ、新会長に中村彰男氏を、以下相談役、副会長、会計、監査、世話人など
総勢20名を選出、2年間の任期で取り組むことになりました。
次に、「平成29年度の活動計画案、予算案」が審議され原案が承認されました。
新年度も毎月の「連続学習会」を中心として、ひきこもりの知識と対応を学び、相談活動の充実や
交流会、講演会なども織り込んで、皆さんに役立つ「家族会」としていきたいというものです。
◇例会と連続学習会日程表
|
月 |
日 |
学習会テーマ |
講 師 |
会 場 |
|
4 |
9 |
ひきこもり・親の取り組みは必要 |
桝田宏子先生 |
番町センター |
|
5 |
14 |
親の生き方・子どもの生き方 |
菊池 恒先生 |
番町センター |
|
6 |
11 |
もう一度ひきこもることの意味を考える --存在論的ひきこもり論から |
評論家 芹沢俊介氏 |
あざれあ |
|
7 |
9 |
長期化する事例を考える |
NPO法人教育研究所 所長 牟田武生氏 |
あざれあ |
|
8 |
13 |
体験を語る(仮) |
清水美子さん |
番町センター |
|
9 |
10 |
つながる・かんがえる対話交流会(仮) |
KHJ本部 |
あざれあ |
|
10 |
8 |
(未定) |
(SCS予定) |
あざれあ 5F |
|
11 |
12 |
ひきこもりを多角的に捉えてみる |
菊池 恒先生 |
あざれあ |
|
12 |
10 |
会員交流会 |
|
番町センター |
|
1 |
14 |
(未定) |
(未定) |
未定 |
|
2 |
11 |
(未定) |
(SCS予定) |
未定 |
|
3 |
11 |
(未定) |
(SCS予定) |
未定 |
◇開催は毎月第2日曜日です。8月も会場の都合があって盆休みもありますが第2です。
◇講師は、桝田宏子先生は、SCSカウンセリング研究所 代表
菊池 恒先生は、人間関係と心の相談舎 代表
<例会日のタイムスケジュール>
10;00~12;00 準備会(例会の準備で、文書配分・打ち合わせなど)
12;00~13;00 昼食、懇談(ここまでは自由参加です。都合のつく方は是非お出かけ下さい。)
13.00~13;15 例会受付
13;15~13;30 例会開会、連絡事項など
13;30~16;30 連続学習会(休憩、質疑応答、全体懇談を含む)
初めての方などで、よろしければ終了後に相談にのらせていただきます。
尚、例会の参加費は、共同募金の助成金が決定しましたので、会員皆さんの負担軽減のため
平成29年度中は、「一家族500円」とさせていただくように決まりました。
又、役員中心に運営しておりますが、会の運営には色々な準備やら役割があります。役員も当事者を
抱えた同じ立場ですので「これ位なら手伝える」など、多くの方のご協力をお願いします。
会長就任の挨拶
のっけから恐縮ですが私は演歌が好きで、特に美空ひばりは聴けば聴くほど、唄えば唄うほど味がでてくるものであります。都はるみに「夫婦坂」という曲があります。無論日々茨の道を歩む夫婦の希望の明日へ向かってのエールです。
この坂を越えたなら しあわせが待っている そんなことばを信じて 超えた七坂四十路坂
私はふと思うことがあります、この坂は何時まで続くのであろうか、坂が終えることはあるのだろうかと。
人生七坂、苦労七坂。私にも四十路の時がありました、遥か昔に。今や息子が四十路に近づこうとしております。
長期高齢化の波が全国を覆い、ひきこもりは子供対象のワードではなく、全世代にわたる社会事象となっています。目先の解決策はありません。重い腰を上げざるを得ない行政の支援は後追いです。私たち自身が寄り添い続け、策を体現して行くしかありません。皆さんと一緒に学習を重ね、情報を集め、叱咤激励しながら歩んで行きましょう。坂はいつか超えられます。皆さんのご協力ご尽力をお願い申し上げます。
中村 彰男
4月例会のご報告
4月例会は、4月9日(日)静岡市番町市民活動センターで開催しました。
◆準備会 10時~
15名の参加をいただきました。
まず「いっぷく会便り4月号」などを入れて参加者への配布、欠席者・関係機関への郵送作業を行いました。そしていくつかの報告事項、打ち合わせ事項について話し合い、あとは昼食をとりながら楽しい歓談の時間を過ごしました。
場所も例会場と同じですので、弁当持参ですが、例会に少し早めに出かける感じで参加してみて下さい。
親の居場所でもあります。是非とも楽しい時間を共有しましょう。
◆例会 13時15分~16時40分 司会進行; 参加者35名
◇平成28年度総会 別記のとおりです。
◇連続学習会 14時20分~16時40分テーマ「ひきこもり・親の取り組みが必要」
講師;SCSカウンセリング研究所 代表 桝田 宏子先生
桝田先生は、長年にわたりひきこもり問題に取り組んでこられ、試行錯誤を繰り返してきたが、最後は一番身近な「親の取り組みが絶対必要」であるとの思いに至っている。
今日の話のポイントは次のようなことでした。
・親の取り組みがないと本当の回復は難しいです。
「親が変わらなければ子どもは変わらない」と言われていますが、最近は親も焦っていますね。
「親が死んだらどうする?」ということも目立つようになってきた。そうすると経済的なサポートしなければ駄目だろうと・・なってくるわけですが、親が生きている間にこのような学習会に参加している人は、案外とちゃんと暮らしていますね。
・自分の気持ちに正直に生きていることが大切です。
「困ったら逃げる」「避ける」「断る」「やめる」「うそつく」嫌なことがあった時にこれができることは自分に正直に生きるということで、人間が生きてゆく上でとても必要なことです。
本当のことを言えない。親にたてつけない人は弱いです。生きていれば嫌なこともいっぱいあります。
それを正直に出せることが良いのです。ひきこもりの子は、やさしくて、正直に本当のことを言えないのですね。
・親も生きていれば色々な事があります。当たり前です。
自分の都合の悪いこと言えないというのは、段々と自分も弱くなるし、子どもも弱くなります。
・色々な事例を上げて、親が否定しないことがすごく大事です。見守ってやるのです。
他人に何と言われようとも家族が大事であるという気持ちです。
・一方で、最近は引き出し屋とか合宿団体など、色々な支援組織が増えています。これを利用する人も多くありますが、一旦回復したかに見えても、あとで元に戻ってしまうことがあります。
・ひきこもりの子を隠したがる親もいます。親が堂々と「今 流行りのひきこもりです」と言える位で。
僕は隠された子ではなかった。子どもは見ていて感じます。
・年齢も高くても大丈夫です。親の取り組み次第です。十分間に合います。
・子が親の介護ではなく「虐待してやるぞ」これはその時の本音が言えている。無条件肯定で見ると「本音が言えている」良いことと受け止める。そうすると心が変わってくるのです。本音を正直に。
・よく出る言葉で「死にたい」と言った時に「死なないで生きていて」という言い方は「反論」していることになる。「成るべく生きていて下さい」と言えば反論ではない。「そう・・」「死に方考えているの?」こんな対応もありますね。
・皆さんの子どもは「頭がいい」「感度がいい」「やさしい」、これらが逆に反目になった人達ですから、子ども時代に、あまり子供らしく過ごしていないですね。親が困るだろうというようなことはやっていないのです。もう一度育ち直しをすると結果は必ず出ます。
・日本には昔から「つばなれ」という言葉がありますね。「一つ」から「九つ」で「十」は「つ」がありません。これは「9歳までは可愛がれ」という伝統的な教えがあります。多分皆さんの子どもは利口なのを口実に早めに切り上げていますね。9歳までは可愛がる、抱きしめてやるのです。
・不安定な世界では、親子、兄弟、家族など最小単位がとても大事な時代になります。
・どんな相手に対しても、きちんと自分を主張し、同時に不要な衝突や孤立を避ける事ができる。
「自立」とは、人に頼れること。助けを求められること。
他人に迷惑をかけないということは、自立ではありません。
書籍「愛着障害」--子ども時代を引きずる人々-- 岡田尊司著(光文社新書刊)紹介
はじめにー本当の問題は「発達」よりも「愛着」にあった。
「人間が幸福に生きていくうえで、最も大切なものーそれは安定した愛着である。愛着とは、人と人との絆を結ぶ能力であり、人格の最も土台の部分を形造っている。人はそれぞれ特有の愛着スタイルをもっていて、どういう愛着スタイルをもつかにより、対人関係や愛情生活だけでなく、仕事の仕方や人生に対する姿勢まで大きく左右されるのである。安定した愛着スタイルをもつことができた人は、対人関係においても、仕事においても、高い適応力を示す。人とうまくやっていくだけでなく、深い信頼関係を築き、それを長年にわたって維持していくことで、大きな人生の果実を手に入れやすい。どんな相手に対してもきちんと自分を主張し、同時に不要な衝突や孤立を避ける事ができる。困ったときは助けを求め、自分の身を上手に守ることで、ストレスからうつになることも少ない。人に受け入れられ、人を受け入れることで、成功のチャンスをつかみ、それを発展していきやすい。」(以下略)
・この子のおかげで、こういう心理学も勉強できることもありがたいですね。
回復は約束されています。但し、親が続ければです。頑張りましょう。
概略こんな学習会をして頂きました。ありがとうございました。
平成28年度版 学習会記録集を作りました
いっぷく会は、親の学習会を中心に活動しています。毎月の「いっぷく会便り」でその内容の報告をしておりますが、昨年度に続き「平成28年度連続学習会記録集」を作成しました。
印刷費もかかっておりますので、一部200円のご負担をお願いします。希望者は、例会にご出席の折にお買い求めください。尚、郵送希望の方は事務局まで申し込みください。
「個別相談会」のお知らせ
日時:平成29年 6月3日(土) 9:30 ~ 21:00
4日(日)
9:30 ~ 18:00
場所:静岡市番町市民活動センター 2階
大会議室
(カウンセラー) 「人間関係と心の相談舎」代表 菊池 恒 先生
相談時間 1家族=50分 80分 110分の各コース(会員限定・有料)
お申込み・お問い合わせは TEL・FAX 054-245-0766(中津川)まで
6月例会のお知らせ
日時 :平成29年 6月11日(日) 13:15 ~ 16:30
会場 :静岡県男女共同参画センター 「あざれあ」 4F・第2会議室
<連続学習会テーマ>
『もう一度ひきこもることの意味を考える ― 存在論的ひきこもり論から 』
(講師)評論家 芹沢 俊介 先生
(参加費)今年度も、赤い羽根共同募金からの助成金交付が決定致しましたので、一家族、ワンコイン!500円とさせていただきます。
初めて参加される方は、体験日として無料で参加できます。
当事者の方は、いつでも自由に無料で参加できます。
尚、当日10:00より例会準備会を同場所で行っています。会報の発送作業や家族同士の歓談などを行っています。家族、当事者の方などどなたでも参加できます。むしろ、来ていただく方が多いほうが準備の都合上助かります。例会時とはひと味ちがった雰囲気で、気楽なお話も出来ますよ。
また、居場所として活用するのもひとつの方法です。是非、皆さんのご参加をお待ちしています。
「ひきこもり支援」被害続出 「静岡新聞」 平成29年5月1日記事より
ひきこもりの人の自立支援をうたう業者に、実態のない活動名目で多額の契約料を支払わされるなどの被害が各地で相次いでいる。
関東在住の20代女性と母親は4月、家族間のトラブルを相談した東京都内の業者を相手取り、慰謝料など約1700万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
女性は自宅から無理やり連れ出され、暴力や脅しで軟禁状態に置かれたとしている。
3ヵ月分の契約料約570万円を支払ったが、支援は行われなかったという。
内閣府調査では、ひきこもりは全国に54万人(15~39歳)で長期化、高年齢化が進む。
公的な相談窓口が限られる中、就労訓練などを掲げる民間業者が各地で急増。拉致・監禁まがいの手口で連れ出し、高額の料金を請求する「引き出し屋」と呼ばれる悪質業者の存在も指摘されている。国民生活センターには「工場で働くと説明されたが場所を教えてくれない」「子どもに会いたいと言っても『親を憎んでいるから』と拒否される」など複数の業者に関する相談が寄せられ、国による実態把握が急務だ。
(以下略)
「いっぷく会」では、SCSカウンセリング研究所を中心に講師をお招きして毎月学習会を開催しております。ひきこもりからの回復には、「一番身近な親が正しく理解して対応する」ということを学んでいます。
社会問題化してきたことにより、各種民間業者が出てきております。お気をつけ下さい。
上杉さん(前会長、現相談役)、本当に長い間お疲れさまでした。誠にありがとうございました。
会員の皆さま、今年度からは中村新会長のもと、力を合わせて情報発信を行っていきたいと思いますので、何でもかまいませんのでご意見ご投稿をお願いします。
hk@編集子
初めてご参加の方、初回は体験として無料です。その後よろしければいつでも入会手続きができます。年会費は6000円で、出席した時には参加費のご負担をお願いします。
その他、いっぷく会へのお問い合わせは事務局までお願いします。
事務局 電話・FAX 054-245-0766 担当 中津川
連続学習会は「赤い羽根共同募金」の助成を受けて運営されています。