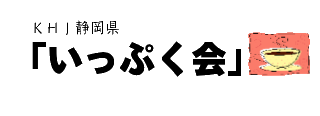活動内容
いっぷく会便り 2020年11月号
令和2年11月1日 発行
NPO法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会 静岡県「いっぷく会」
会長 中村 彰男
|
日時
|
2020年10月11日(日)
|
|---|---|
|
テーマ
|
「親を信じはじめたら起きること」
|
|
講師
|
SCSカウンセリング研究所 カウンセラー 臨床心理士 公認心理師 坂本 崇代氏
|
|
会場
|
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
|
PDFファイル202011.pdf![]()
10月例会のご報告
10月例会は、10月11日(日)静岡県男女共同参画センター「あざれあ」5F第3会議室で開催しました。
◇準備会 10時~
14名の参加をいただきました。まず「いっぷく会便り10月号」「11月個別相談会案内」などを入れて出席者への配布、欠席者・関係機関への郵送作業を行いました。
そしていくつかの報告事項、打ち合わせをして、各種情報などについて話し合いました。あとは昼食をとりながら楽しい歓談の時間を過ごしました。弁当持参ですが、どなたでも例会に少し早めに出かける感じで参加してみて下さい。都合のつく時間からでも構いませんので、是非とも楽しいゆっくりとした時間を共有しましょう。
◆例会 13時15分~16時30分 参加者29家族32名参加でした。
◇連続学習会
テーマ「親を信じはじめたら起きること」
講師 SCSカウンセリング研究所 カウンセラー 臨床心理士 公認心理師 坂本 崇代氏
坂本先生の学習会は、今年1月に次いで2回目となります。最初に職歴を含めての自己紹介がありました。
異色の道のりを経て現在に至っています。そして、SCSカウンセリング研究所を主体に幅広くご活躍されています。
自己紹介に続いて、SCSカウンセリング研究所の基本的な考え方や特徴の紹介、特に大前提である『無条件肯定』の「肯定」は、親の「肯定」ではなく、子どもにとっての「肯定」でなければならない。
そして、「きく」の違いの説明があり、「きく」には、①訊く(ask)尋ねる、質問する、②聞く(hear)耳に入ってくる、③聴く(listen)自ら意識的に集中してきく、全身全霊を集中させてきく、があり、子どもと接する時には③の「聴く」であることが大事とのことです。
本日のテーマは、ひきこもっている我が子が、親を信じはじめたら起きることです。主語は、「親」ではなくて、「子ども」です。ここがポイントです。どうやったら親を信じはじめることが出来るのか、そして親を信じるとはどういうことなのかを含めて学習していきましょう。
1.親を信じるとはどういうことか
①子どもは、今までどう生きてきたか
・繊細で感度が高い
ひきこもっている人は、コミニュケーションでの相手からの受取り方が非常に繊細で、また感度が高い人が多いので、ごまかしが効きません。
・親から見た「いい子」をしてきた
本人は意識していない場合いが多いのですが、自分の気持ちよりも周りを優先してきた。家庭内のバランスを取る役目も担ってきたこともあり、親としては手のかからない子で育てやすかった。
その反面親の目が行きわたっていなかったことで、エピソードが極端に少ないのです。
・反抗期をしていない
ひきこもっている人は、ほとんどの人が反抗期をしていないのです。家庭が安心安全な場所として機能していない場合、反抗することで家庭が壊れてしまうためです。
・自分だけで抱え込む
ひきこもっている人は、これも無意識の場合が多いのですが、自分の本心を封じこめて我慢し続ける人が多い。自分だけで抱え込むことによって生きるエネルギ-を失い、その結果ひきこもりとなってしまうのです。
・親を守って生きてきた
本人は無意識のうちに親を守って生きてきました。親をどんなふうに守ってきたかという視点も重要なポイントです。
②安全で安心な環境を提供する ~ 安心してひきこもらせる
家全体を安全安心な状態にしなければなりません。そのためには、先ずは、親が安全・安心な人にならなければなりません。親が作ったものを一切食べないこともあります。これは、親の愛情を重く感じるためや反抗の意味合いもあり受け入れられないのです。それが、段々と食べてくれるようになれば、少しは親を信用しはじめたということです。自分の部屋で食べていたのが、食卓で食べるようになることは、食卓が安全な場所になってきたということです。
安全で安心な環境を作るには、
・子の全てを肯定していく
我が子の行動、言葉の全てを肯定して下さいね。
・子の後ろから支えてついていく
親が子どものためにと転ばぬ先の杖をいっぱいなげ過ぎて、挙句の果てにその杖につまづいてしまいます。後ろからそっと支えてあげることが大切ですね。
・お小遣いをあげる
欲求が出てきた時に自由に使えるお金が必要となるものです。小遣いも親の愛情の証であり反抗して受取らない場合がありますが、見える場所に積んで置くようにして下さい。
2.親を信じたら起きてくること
①社会的欲求が出てくる
家庭は第一社会であり、家族への関わりの欲求が出てきます。
②しなければならない(have to)と ~したい(want to)
この配分が変わってきます。大きく占めていた「しなければならない」が、段々と欲求である「したい」に変わっていきます。
③トラブル(trouble):問題、困難とは
・親から見れば、一見ネガティブな出来事ですが、本人にとっては必要なことです。意識無意識に関わらず、人の反応や態度や言葉や行動には必ずその人なりの理由があるからです。
・ひきこもっている子を悪者or家族の敵にしていないか。ひきこもりの問題は本人のみの問題では無くて、子を含めた4世代ぐらいの家族全体の問題だと認識して下さい。
SCSの目指すものは、自己実現欲求です。これは、自分は自分で良いと思え、それが周りからも認められて、自分が幸せだと感じられるところを回復と考えています。
④吐き出し
吐き出しの特徴としては、
・恨みやつらみなど過去のネガティブな事を言ってくる場合が多い
・親が悪いからこうなったなどと人のせいにしてくる
・繰り返し繰り返し同じ話をしてくる
罪悪感、失望感で自分を責めていたそのベクトルが外に向かって行こうとするタイミングなのです。
人のせいにするのも外に向けたベクトルなのです。
受け取ってくれる両親がいるからこそ起きるものであり、吐き出しに対しての正論やジャッジは厳禁です。親がちゃんと受け止めることによって、吐き出しのストーリーが変わり、本心を喋り出すようになります。そして、本人は吐き出すことによって、段々と自分の良い面を見ることが出来るようになります。すると、他人の良い面を見ることが出来るようになるのです。気が済むまで聴いてあげることが大切です。
⑤退行
退行とは、心理的危機に陥った時に、発達段階の前段階に戻り、対応しようとする無意識での心理的働きのことです。吐き出しと同様に、親を信じてきたからこそ起きるものです。
健全な人は普段から、母親に甘えたように頼みごとをする、首に巻いたタオルを噛む、など上手に退行を使っていますが、ひきこもりの人は、今まで退行を使えなかった、または使わないできた人が多いのです。
なぜ退行を使えなかったのだろうか。家の中で弱いところを出していることであり、それによって家族に迷惑をかけやしないかと、周りを優先しているから素直に出せないのです。ひきこもりになってから出てくる退行は結構大きなものがあり、本当に幼児に戻っている場合もあります。
退行の内容を見て何歳ぐらいに感じますか、その年齢の時に本人にとって重要な局面があったのです。
これも大きなヒントとなります。
⑥暴言・暴力
なぜ暴言・暴力になるのか。最初は一生懸命に言葉で伝えようとしますが、それがなかなか伝わらないために暴言、暴力へと繋がってしまうのです。
暴力になる場合は、本人なりに何らかの意味があるものです。暴力は、その表現なんだと受け止めるようにして下さい。
「死にたい」と言ってくる場合がありますが、これはチャンスです。親を信じている証拠で、多くの場合は他人に訴えるものなのです。どうして「死にたい気持ち」になっているかを聴いてあげて下さい。
「死にたい」「死ね」「殺す」ですが、最初は「死にたい」で始まり、「死ね」「殺す」となっていきます。
自分に向かっていた「死にたい」が、「死ね」「殺す」と外に向かうのは、自分の負の感情を親にぶつける事が出来ているのです。
自分の不甲斐なさなどに対する怒り(第二感情)のエネルギーが大きいために暴言・暴力となるのです。
暴力に対しては、限界を設定して下さい。子どもを犯罪者にしないためにも警察(生活安全課)との連携も必要です。
3.まとめ
・回復はおおむね段階的に進んでいきますが、基本的には、本人の後ろに付いて行きながら、本人が出してきたものに寄り添って下さい。
・親の在り方が変わると、親を信じられるようになり、子どもは自分の心に光が当たるようになるのです。評価無しで子どもを見ることが出来ているかが大切です。
・元気な木を思い浮かべて下さい。子どもはどんな木に見えていますか。「言の葉を追いかけるな、木を見ろ」です。言葉、行動のみに捕らわれないで全体を見ることが重要です。
・メタ認知の視点も大切です。ちょっと離れた所から見ることも大切なことです。
質疑応答から
・ひきこもりの子どもを抱える家庭では、たわいない会話が少ないようです。増やしましょう。
・相手を肯定するには、自分を肯定出来なければ出来ないことです。親自身にとって大事なことです。
・反抗期とは、親が神様のような存在から普通の人間になっていく過程です。
・部屋の状態は、心理状態を表していることが多いです。
今日は、色々な実例を踏まえて学習をさせていただきまして、ありがとうございました。
12月例会のお知らせ
日時 :令和2年12月13日(日) 13:15 ~ 16:30 (受付 13:00~)
会場 :静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 4F 401研修室
連続学習会テーマ: 『 事件に学ぶひきこもり対応 ~ 経験者・相談員の立場から ~ 』
講師:ヒューマン・スタジオ 代表 丸山 康彦氏
<参加費>1家族 ワンコイン! 500円、初参加の方、当事者の方 無料
尚、当日10時より同場所で準備会を行っていますので。お気軽に是非ご参加下さい。
◆新型コロナの状況により、変更せざるを得ない場合がありますのでお含みおき下さい。
受付当番 : □富士市以東 □静岡市駿河区、清水区 ■静岡市葵区 □藤枝・焼津市以西
■の地区の方よろしくお願いします。
「個別相談会」のお知らせ
日時:令和 2年 11月20日(金)、 21日(土)、 22日(日)
場所:静岡市番町市民活動センター 小会議室
(カウンセラー)「人間関係と心の相談舎」代表 菊池 恒 先生
相談時間 1家族=50分 80分 110分の各コース(会員限定・有料)
お申込み・お問い合わせは TEL・FAX 054-245-0766(中津川)まで
会則についてのお知らせ
「KHJ静岡県いっぷく会」の会則を最近の入会の方にお渡ししてありませんでした。会のホームページにも掲載してありますので、それをご覧いただければとは思いますが、今後、例会日には文書でお渡しできるように準備しておきますので、必要な方はどなたでも申し出て下さい。(事務局)
《会長コラム》
このところ毎晩華麗なる天体ショーが夜空に展開されているのを皆さんはご存知でしょうか。木星、火星が地球に大接近して明るさを増し、その間に土星が顔を出して、木土火と月が天頂にほぼ一直線に並ぶという極めて珍しい現象です。ロマンチックな気分に浸り、暫し世の憂さを忘れさせてくれます。もしこの星空の何処かに地球を眺めている文明があるとしたら、果たしてどのように映っていることでしょう。
恐らく呆れ返っているのでは、環境は汚しっぱなしで戦の絶えることはなく、多くの国で身勝手な指導者が跋扈している現実を。
昼も夜も空を仰ぐことを心掛けています。一年で最も過ごしやすい季節の今、皆さんにも是非お勧めしたいと思います。我が息子にもたまには遠くを見なさいと促しているのですが。
初めてご参加の方、初回は体験として無料です。その後よろしければいつでも入会手続きができます。年会費は6000円で、出席した時には参加費のご負担をお願いします。
その他、いっぷく会へのお問い合わせは事務局までお願いします。
事務局 電話・FAX 054-245-0766 担当 中津川
E-mail:ippuku-kai@outlook.jp
本会の活動は「赤い羽根共同募金」の助成を受けて運営しています。