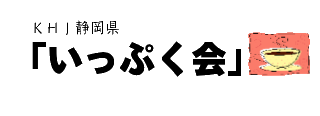活動内容
いっぷく会便り 2020年6月号
令和2年6月1日 発行
NPO法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会 静岡県「いっぷく会」
会長 中村 彰男
PDFファイル202006.pdf![]()
特別学習会からの報告
新型コロナウイルス問題の発生で3月~5月の例会(連続学習会)を中止させて頂きました。
この間の「いっぷく会便り」は講演会の報告、菊池先生からのメッセージを頂きお伝えしてきましたが、今月号は、昨年度「特別学習会」として開催したものを報告します。
これは、新しく加入された会員を中心に「なぜ親の学習が必要なのか、親が変わらないといけないのか・・」、いっぷく会の基本となる部分でありますので、ご理解を深めて頂くように学習したものであります。
当日は、講師の話を約1時間余、参加者からの質問に約2時間にわたり答えて頂きました。
2019年5月25日(土)静岡市番町市民活動センター中会議室で開催。(13家族15名出席)
テーマは「ひきこもりからの回復に向けて 親の役割とコミュニケーション」
講師;SCSカウンセリング研究所 副代表 藤江幹子氏(KHJ千葉県「なの花会」理事長)
1、ひきこもり(不登校)を理解する
「うちの子はどうしてひきこもったのかな?」と考えた時に、ひきこもりをマイナスで捉えていると子どもの良い面が見れないし、子どももそれを感じて「親は自分のことを良く思っていない、別の目線で見ているな~」と思うと心は閉じたままで開きません。温かい眼差しを感じると「緊張と恐怖でコチコチになっている心」が自然と柔らかい心になってゆくのです。
私たちは長い間、どうしても世間体が大事だったりして周りに合わせながら生きてきています。常識感とか世間体とかから外れている本人を肯定的に見ることができないのです。まず親がそれまでの価値観、世間体を外すことが大事です。本人たちもそこから外れているけれども、親と同じで超真面目、世の中の価値観、常識感がしっかりある人たちなのです。だから自分の現実を受け入れられないのです。
まず親が先にやらないと辿りつけないのです。
親が元気になり、本人を理解し続けて、変わることによって子は変わってゆくのです。
学習しながら「生きていればいいじゃん」そう考えると自分も楽だし、子も楽になります(伝わる)。
思いと現実の間の葛藤で苦しみが生じている。一足飛びにはいきません、元気になるには時間がかかるのです。根気よく、諦めず、行きつ戻りつです。一般的な人と比較しないことが大事です。
2、回復に必要な親の役割
①大切な親の姿勢
まず子どもの気持ちが理解できないと本人のサポートは出来ないし味方になれません。親は子どもの一番の理解者になってあげる、それが基本です。
自分の家で不登校、ひきこもりの子がいる「さてどうしよう?困ったな」「私のあそこが悪かったのかな?」思い当たることいっぱい出てきて、はじめは自分を責めてしまう、しかし自分を責めて元気になるならともかく親も子も元気にならない。子どもはよくわかるのです。何も言わなくても親の顔を見たり、動きを見ていて、親がどんな気持ちでいるのか?
自分に対してどう思っているのか読んでしまうのです。心が見えすぎてとても生き難さを感じている。(言葉に出さなくても)
親自身が自分に「自己肯定感」をもてなくて、子どもに自己肯定感をもてと言っても無理です。
元気になるということは自己肯定感をもつということで、親は自分を責めない。とても大切です。
こういう親の会に来ると「自分だけではないんだ」という、仲間がいると気持ちが楽になるものです。
会に入ることで、情報から孤立しないのも良いです。学ぶことによって、今まで自分の世界、自分の体験の中でしか考えてこなかったことが、他の人の話を聞くことで変わってくる。感じてくるのです。
勉強しても2~3年で「大丈夫かな?」それをやっても子どもは変わらなかったりして、それぞれの立ち位置が違うのでステップアップが異なるが、一足飛びにはなりません。根気よく取り組むことが大事です。親が元気になり、本人を理解し続けて変わることによって子は変わってゆくのです。
兄弟姉妹のこともありますが、難しいものがあります。家の中で良い雰囲気になることが大事ですので、基本的には兄弟姉妹にはあまり頼らない方が良いです。中々理解してくれません。でも親が亡くなった後兄弟で面倒を見ている人もあります。
②親の無条件の肯定的関心が必要
ひきこもりからの回復には、子どもがどんな状況にあってもそれを肯定的に受けとめる。
具体的に言うと「昼夜逆転も」親も気になるところだが本人としては理由があるのです。「風呂に入らない」「一言も話さない」「顔も見せない」「無視している」「イライラしている」「不平不満を言ってる」すべて受け入れてゆくのです。なぜそうなのか?
ここで「基本的信頼」ということについて学んだ。このはじめは乳児期に母親(母親的な人)によって育てられます。それから対人関係が段々と広がっていきます。
先ず一人ないし二人の人とゆるぎない信頼関係ができた人が、段々とその他の人との関係を広げてゆくのです。いきなり多くの人と接することは決して良い事ではないのです。赤ちゃんの時に望んだように愛されるということができていないと、思春期・青年期に自分の望んだような愛され方をしようとします。時には暴力を用いてでも相手に言うことを聞かせようとします。
母性性とは、相手が望んでいるようにしてあげるということです。社会が要請することを子どもにさせるのは、父性的な役割ですが、それは子どもがもっと大きくなってからの事です。
基本的信頼がしっかり育っていなければ、何歳になっても父性的な働きかけをすることはできないのです。望むことを十分にしてもらうと、子どもは自分を信じることができるようになるのです。
基本的信頼は人間に希望を与えます。
そのために無条件の肯定的関心から入ってゆく、それが基本です。
人として、誰でも無条件肯定はうれしさ、力強さを感じたりして生きる力になります。
③家が安心できる環境である
本人にとっての社会は「家」だけなのです。家の中に住んでいる人が本人にとっては社会なのです。
だからその社会(家)がどんなに大切か、不安定であっては元気にならない。そのために親が勉強して家の中が安心できるように整えてゆきましょうと言うのが基本です。
そして本人が安心をもつには親自身が安心をもつことが大事です。
こうして回復してゆくんだと分かると安心感が生まれます。
自分が生きていていいのか悪いのか? 自分は価値のない人間ではないか?親にとって自分は不要な人間ではないか? そんなことを本人たちは感じています。
それでも「生きていていいんだ」「存在していいんだ」と本人が感じられるように親が丸ごと受け入れることが大切です。
又、これには夫婦関係も大事です。一緒に学ぶことで両親の一致度が高ければ家の中の安定感も高まります。本人にとって迷わなくて済むのが心強いです。
3、親子のコミュニケーション
①親の言葉
正論・批判・指示・命令・干渉・激励など親の価値観を押し付けないことが大切です。
丸ごと受け入れる言葉を出してあげると良い。
誕生日メッセージなどで、メールを使うのも普段言葉では言えないことを伝えられますね。
②対話は続ける。
肯定する会話。関心を持つ、会話のリソースを増やす。それを続けることです。
③親子の会話が出来るようになるために
・まず声掛け(挨拶)無視されても続ける。相手が言ってこないのは「怖いとか?」理由がある。
・快話(相づちで聴く、肯定で聴く、魔法の言葉「そう」「そうか~」「そうなんだ」ですね。)
・NOが言える。(安心してくると言えるようになる。家で言えるようにならないと外で言えません。)
・本音が言える(愚痴が言える、弱音が吐けることがとても良いことです)
4、他人との関わりの工夫
①親が社会と繋がる
先ず親が、家族会・支援機関、医療機関などと繋がる、動いてみる。情報を得ておくと良いです。
そして必要により親子で動いていくようにつなげてゆくと良いです。
②第三者との関わり―1対1から
幼児期の母との世界(2者関係の世界) ⇒ 学童期、母以外の家族メンバーとの世界、地域の子ども集団の世界 ⇒ 思春期、青年期、仲間の世界、より成熟した群れ社会 ⇒
成人期、父なる世界、生存競争の世界、現実の世界へと広がっていきます。
③社会への入り口
居場所・デイケア・ボランティア・サポートステーション・中間就労など様々なものがあります。
本人にとってどれから進めるのが良いのか、情報を得ておき利用をしてゆくこともできます。
5、回復途中でおきる様々な現象
回復の段階において様々なことが起きてきます。
退行・反抗・暴言・暴力など。これらは回復段階でおきてきますので、その対応を学んでおきたいことです。とても重要なことです。
6、回復の目標をどこにおくか。就労??
どうしても最終的には回復して「仕事をしてもらいたいな~」と、社会に出てもらいたいと誰でも思います。でもその部分は後なのです。まずは母性の中で受け入れられることが大切なことです。
7、その他
・お小遣いの話 お金は生きる力をくれます。小遣いをやらないというのは動かなくてよいというのと同じで危険です。元気が出てくると欲しいものも出てきます。あとで必ず役に立ちます。
例え「いらない」と言ってもどこかに置いてやる。それは何に使っても全く自由と思うことです。
その他にもたくさんのお話を頂きました。ありがとうございました。
7月例会のお知らせ
日時 :令和2年7月12日(日) 13:15 ~ 16:30 (受付 13:00~)
会場 :静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 4F 第1研修室
<連続学習会テーマ>
『 支援センター開設6年を振り返って 』
講師:静岡市ひきこもり地域支援センター「DanDanしずおか」相談部長 NPO法人サンフォレスト 理事長 三森 重則氏
<参加費>1家族 ワンコイン! 500円、初参加の方、当事者の方 無料
尚、当日10時より準備会を同場所で行っています。会報の発送作業や家族同士の歓談などを行っています。是非ご参加下さい。
◆新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、変更せざるを得ない場合がありますのでお含みおき下さい。
受付当番 : □富士市以東 ■静岡市駿河区、清水区 □静岡市葵区 □藤枝・焼津市以西
■の地区の方よろしくお願いします。
書籍の斡旋
下記の書籍は例会場で斡旋しています。ご希望の方はお買い求め下さい。
・親から始まるひきこもり回復 SCS副代表 桝田智彦著 2,000円
・中高年がひきこもる理由 SCS副代表 桝田智彦著 1,000円
・新版 ひきこもりのライフプラン「親亡き後」をどうするか 斎藤環・畠中雅子共著 800円
「2019年度の連続学習会記録集」 冊子にして頒布 有料200円
ひきこもり対応の応援歌
青少年交流スペース「アンダンテ」様から提供いただきましたので順次ご紹介します。
“ ひきこもり 責めず咎めず 受けとめる こうなるのには みな訳がある ”
“ こもる訳 子は容易には 喋らない 子どもには子の面目がある ”
“ こもる子に 直せ変われと迫るのは 子を追い詰めて 苦しめるだけ ”
「いっぷくサロン」の再開について
4月から休止していましたが、6月14日の例会過ぎから再開します。
6月16日(火)から毎週火曜日、木曜日の午後1時~4時までです。
尚、お出かけにあたりましては「マスクの着用」などお忘れなくお願いします。
《会長コラム》
ご無事ですか?この挨拶を交わすようになって久しくなります。今コロナはどの辺りなのでしょうか。
まだ拡大途上なのか、ピークは過ぎたのか、 終息に向かいつつあるのか誰にも分かりません。グローバル化の進んだ世界で 再び人の行き来が緩和されれば、第2波第3波の恐れは十分に予想されます。
このような危機的状況の中で炙り出されて来たものが「格差の拡大」「政治の貧困」であります。昨日一律10万円支給の申請書がやっと届きました。今となっては、どのような趣旨であったのかも分からなくなりました。アベノマスクなど何処を漂っているのやら。両方とも突き返してやりたい気分です。この国にはコロナよりも悪質なウイルスが長期にわたり万延しているようです。
初めてご参加の方、初回は体験として無料です。その後よろしければいつでも入会手続き
ができます。年会費は6000円で、出席した時には参加費のご負担をお願いします。
その他、いっぷく会へのお問い合わせは事務局までお願いします。
事務局 電話・FAX 054-245-0766 担当 中津川
E-mail:ippuku-kai@outlook.jp