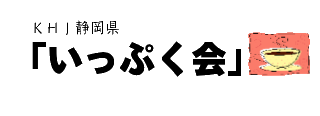活動内容
いっぷく会便り 2020年10月号
令和2年10月1日 発行
NPO法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会 静岡県「いっぷく会」
会長 中村 彰男
|
日時
|
2020年9月13日(日)
|
|---|---|
|
テーマ
|
「我が子が出しているサインに寄りそう」
|
|
講師
|
SCSカウンセリング研究所 副代表 KHJ千葉県なの花会 理事長 藤江幹子氏
|
|
会場
|
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
|
PDFファイル202010.pdf![]()
9月例会のご報告
9月例会は、9月13日(日)静岡県男女共同参画センター「あざれあ」4F研修室で開催しました。
◇準備会 10時~
11名の参加をいただきました。まず「いっぷく会便り9月号」「9月個別相談会案内」「10~12月学習会案内」などを入れて出席者への配布、欠席者・関係機関への郵送作業を行いました。
そしていくつかの報告事項、打ち合わせをして、各種情報などについて話し合いました。あとは昼食をとりながら楽しい歓談の時間を過ごしました。弁当持参ですが、どなたでも例会に少し早めに出かける感じで参加してみて下さい。都合のつく時間からでも構いませんので、是非とも楽しいゆっくりとした時間を共有しましょう。
◆例会 13時15分~16時30分 参加者28家族31名参加でした。
◇連続学習会
テーマ「我が子が出しているサインに寄りそう」
講師 SCSカウンセリング研究所 副代表 KHJ千葉県なの花会 理事長 藤江幹子氏
この学習会も、今までも学んだことと同じようなことが何回も出てきますが、私たち人間は忘れる生き物なのです、繰り返し 繰り返しやって段々と身についてくるものなのです。回復には、早い場合もありますし、時間がかかる場合もありますが、親が取り組めば必ず成果が出てきます。今日も一緒に学習してまいりましょう。
1.我が子の出してきたサインに気付く。
なぜ、わが子がひきこもったか知っていますか? 本人はなかなか話してくれませんね。
原因探しということではなく、心の中の気持ちはどうだったか?
皆さんは、ひきこもりは「問題行動」としてとらえますか? 実はこれは「心のサイン」なのです。
ひきこもる人たちには似たところがあって「やさしい」「良い子」「反抗期なし」「自己肯定感が低い」「こだわりが強い」などです。強迫神経症で2時間も3時間も手洗いを続ける子がいます。こだわり続けることで自分を守っているのです。本人にとって辛い作業です。親の期待に添うように、まわりの期待に添うようにやってきた良い子たちです。それが限界に達する。その結果「ひきこもる」という行動になったということです。
皆さんは「ひきこもっているわが子」を心から肯定していますか?
ひきこもる子どもはとても敏感です。元々感度が良いのです。ひきこもる事によって更に不安を抱えながらいる子が元気になるには、「安心安全な環境」が第一なのです。
2.ひきこもる事の大切さ。
安心してひきこもると、心の感覚が戻ってくるのです。
ピントの合わない写真のピントが合ってくる感じですかね。
今は「ゆっくりとひきこもりなさい」と言ってあげられると少しずつ改善するのです。
心からひきこもりを応援してほしいのです。それ位 今の本人にはひきこもることは大切なのです。
繭籠りということがあります。何もしなくても成長すれば殻を破って自分で出てきます。ひきこもりも同じことで、ゆっくりとひきこもったら自然に出てきます。だから応援してほしいのです。
「昼夜逆転」「歯も磨かない」「風呂も入らない」「顔も合わせない」色々な状態が現れてきますが、そんな時に親はつい何か言いたくなってしまいます。
親が正論で「こうしなさい」「ああしなさい」と、指示命令して正そうとするのは全くのマイナスです。
ひきこもりの人達は「不合理な信念」「思い込み」を持っていて親には理解できないことが多くあります。それでも丸ごと受け入れるのです。
親が覚悟して、「無期限につきあうよ」と取り組んだら必ず変わってきます。
3.家庭を治療の場に。
先に話しましたが家庭を「安心できる環境にする」ことが治療になります。
家の中がいい雰囲気になる必要があります。それには夫婦関係が良いこと、夫婦の考え方が一致していることも大切です。本人たちはとても敏感なのです。だから夫婦が同じ考えで受けとめようとすると安心安全な空気が漂うのです。子どもが突然動き出して驚くことがあります。
ただ兄弟関係は難しい処があります。どうしてもひきこもりの子に親の関心が行くので、他の子どもから不満を抱かれてしまいます。子どもにとって親の愛は平等に欲するものです。親から他の兄弟姉妹への配慮が届くことで、より本人にとって家が安心の場になります。
ひきこもりの子にとっての「社会」は「家庭」なのです。
その社会が安心できるか?
大切なところです。とてもやさしく、敏感で、周りのことを思いやる人、傷つきやすい人なのです。先ずは安心できる環境を作ってあげましょう。それには親が子の気持ちを深く理解をする、気持ちのゆとりも大切です。
それを、わが家では出来ているか? 出来ていないかを考えてみて下さい。
4.妙薬は無条件の肯定的関心。
SCSの基本になっていることです。
条件なく子どもを肯定していくことです。時間もかかるけれどもとても大事なことです。
「どんな状況にあっても否定しない」それがどれだけありがたいことかです。
それが「安心感」につながるのです。一番大事な親から肯定される。
自己否定している当事者にとって、どれだけ力強く感ずるかです。とにかく肯定してあげて下さい。
「子どもがその時味わっているのは、困惑、恨み、恐怖、勇気、愛、なんであっても喜んで受け入れるのです。親が体験するものは所有欲を脱した態度です、親は子どもに条件を押し付けることなく全存在を評価するのです」(カール.ロジャース)
喜んで受け入れるってどういうことだと思いますか? ある方は子どものすべての言動に感謝していますとおっしゃいました。どうぞ皆さん実践してみて下さい。
両親揃って実践してゆくと、家の中の空気が変わってきます。中途半端にならないことです。
特に「無条件」というのは大変な時もあるでしょうが、これ以上の妙薬はありません。
家の中に安心・安全な風土、文化が出来ることでしょう。
ただ「無条件の肯定」と「言いなり」とは違いますのでご注意ください。
「しょうがない」と思ってやるのが「言いなり」。
喜んで「いいよ!」と思ってやるのが「無条件肯定」。いわゆる心と行動が一致しているかどうかです。
「心からいいよ」と思えることが肝心です。
5.寄り添う関わりとは?
「寄り添う関わり」とは皆さんどんなイメージをしますか?
親自身が、今まで生きてきた中で「嬉しかったこと」「ホッとしたり、安心した体験」「良かったこと」を書き出してみた。言葉でのイメージ、行動でのイメージ 色々と出てきました。
「さりげなくやってもらった時」「大事にされた時」「気持ちを分かろうとしてくれた時」「そばにいてくれ、手を添えてくれた時」「ハグしてくれた時」「一緒に背負ってくれた時」など色々と出されたが、ちょっとした言葉や行動で相手がどんな気持ちになるか?
何も言わなくても「そっとハグしてくれた」「そっと手を添えてくれた」行いでも寄り添う関わりはありますね。
そのとき、その場の雰囲気で色々とあることでしょう。
不登校の子どもがいるお父さん。ある時子どもの部屋に行った。子どもは元気無くゴロンと横になっていた。そのお父さん、子どもの横に黙ってゴロンと横になった。何も言わず時間と場所を共有したのですね。それもすばらしい「寄り添い」だと思います。
是非とも「寄り添う関わり」をイメージして色々とやってみて下さい。
親からしたら無駄なことのようでも、子どもにとってはとても大事なことがあります。
今日はこのような学習をしました。ありがとうございました。
11月例会のお知らせ
日時 :令和2年11月8日(日) 13:15 ~ 16:30 (受付 13:00~)
会場 :静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 2F 大会議室
連続学習会テーマ: 『 負の世代間連鎖を阻止する 』
講師:人間関係と心の相談舎 代表 菊池 恒氏
<参加費>1家族 ワンコイン! 500円、初参加の方、当事者の方 無料
尚、当日10時より準備会を同場所で行っています。会報の発送作業や家族同士の歓談などを行っています。是非ご参加下さい。
◆新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、変更せざるを得ない場合がありますのでお含みおき下さい。
受付当番 : □富士市以東 ■静岡市駿河区、清水区 □静岡市葵区 □藤枝・焼津市以西
■の地区の方よろしくお願いします。
居場所となる場所を探しています。
いっぷく会では、家族も当事者も、いつでも自由に利用できるような「居場所」として使える場所を探しています。今の財政状況ではあまり負担はできませんが、適当な場所がありましたら、是非とも役員まで情報をお寄せください。よろしくお願いします。
書籍の斡旋
下記の書籍は例会場で斡旋しています。ご希望の方はお買い求め下さい。
・親から始まるひきこもり回復 SCS副代表 桝田智彦著 2,000円
・中高年がひきこもる理由 SCS副代表 桝田智彦著 1,000円
「2019年度の連続学習会記録集」 冊子にして頒布 有料200円
「いっぷくサロン」 気軽にお出かけください(当番がいます)
毎週火・木曜日 午後1時~4時(但し、祝日、年末年始は除く)
静岡市葵区一番町50番地 静岡市番町市民活動センター2F KHJ静岡県いっぷく会 事務所内
尚、お出かけにあたりましては「マスクの着用」などお忘れなくお願いします。
ひきこもり対応の応援歌
青少年交流スペース「アンダンテ」様から提供いただきましたので順次ご紹介します。
“ 胸の内 聴き留められたと 思うとき 子はおのずから心をひらく ”
“ ひきこもり すべてがダメなわけじゃない 子どもの生きる道はまだある ”
“ 反発と 依存の間 揺れ動く 子の心情を 読まねばならぬ ”
《会長コラム》
若者の自殺が増えているという。特に女性の増加が著しい、由々しきことです。無論長引くコロナ禍がその原因の多くであることは間違いありません。非正規の立場でいつ職を失うかの経済的不安は、正規雇用にも及んであらゆる分野に拡大しています。近年私たちが喪失した最大のものは”絆”です。
夫婦、家族、親戚、地域社会、職場などあらゆるところで”絆”はズタズタとなり孤立化が進んでいます。孤立化を防ぐ手立ては”声掛け”しかありません。制度を整えてお待ちしておりますのではなく、身を乗り出して声を掛けていく姿勢が大切かと思います。
あらゆる場面で声を掛け合うことを実践していきましょう。
初めてご参加の方、初回は体験として無料です。その後よろしければいつでも入会手続きができます。年会費は6000円で、出席した時には参加費のご負担をお願いします。
その他、いっぷく会へのお問い合わせは事務局までお願いします。
事務局 電話・FAX 054-245-0766 担当 中津川
E-mail:ippuku-kai@outlook.jp
本会の活動は「赤い羽根共同募金」の助成を受けて運営しています。