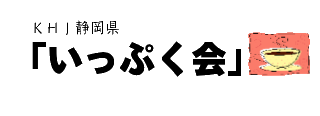活動内容
いっぷく会便り 2020年2月号
令和2年2月1日 発行
NPO法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会 静岡県「いっぷく会」
会長 中村 彰男
|
日時
|
2020年1月12日(日)
|
|---|---|
|
テーマ
|
「 吐き出し、退行、暴言は、回復の始まり 」
|
|
講師
|
SCSカウンセリング研究所 カウンセラー 臨床心理士 公認心理師 坂本 崇代氏
|
|
会場
|
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
|
PDFファイル202002.pdf![]()
1月例会のご報告
1月例会は、1月12日(日)静岡県男女共同参画センター「あざれあ」で開催しました。
◇準備会 10時~
19名の参加をいただきました。まず「いっぷく会便り1月号」、「本部アンケート(本人・家族)」などを入れて、出席者への配布、欠席者・関係機関への郵送作業を行いました。
そしていくつかの報告事項、打ち合わせについて話し合い、あとは昼食をとりながら楽しい歓談の時間を過ごしました。弁当持参ですが、どなたでも例会に少し早めに出かける感じで参加してみて下さい。
都合のつく時間からでも構いませんので、是非とも楽しいゆっくりとした時間を共有しましょう。
◆例会 13時15分~16時30分 参加者41家族49名(初参加5名含む)
◇連続学習会
テーマ 「 吐き出し、退行、暴言は、回復の始まり 」
講師 SCSカウンセリング研究所 カウンセラー 臨床心理士 公認心理師 坂本 崇代氏
坂本先生は、静岡に初めて来られました。自己紹介に続いて、“SCSカウンセリング研究所”の基本的な考え方の紹介がありました。(下記)
◇親育ち・親子本能療法:親が枠(価値観,視野など)を広げることで子どもを生きやすくさせる。
◇無条件肯定:親が子どもを無理に動かすことはしない。
最初に、三人のグループで今我が家で起きていることなどについて話し合い、きき手の“きき方”が、『聴く(listen、自ら意識的に集中してきく)』であることを体感しました。この『聴く』が、我が子の吐き出しを受け取るのに大変大切なことになります。
1.吐き出し
“吐き出し”には、突然大きな声で喋り出してなかなか終わらない大きな“吐き出し”から、会話は全く無く声を掛けても全く返事が無かったが、挨拶の声掛けを続けていたら、いつの間にか小さな声ではあるが「うん」と反応するようになった、など小さな“吐き出し”まで色々です。そして、言語(言葉)での“吐き出し”以外に、気が付いたら食卓のそばに居るようになった、など非言語(行動や態度)での“吐き出し”があります。これも、しっかりとキャッチして下さい。
なぜ、“吐き出し”は起きるのか。それは、受け取ってくれる親がいるからこそ起きることなのです。
“退行”、“暴言”も同じで、親の受け取り方によって、その内容が変化していきます。
安心安全な家庭環境が根付いてくると、家族の中での安心感をベースにして外に出て行こうとします。その外へ出て行く前に、社会的欲求(人と繋がろうとする欲求)が出てきます。社会的欲求には2種類あり家族内での繋がり、その後で家族以外の人との繋がりを求めて行きます。
家族、特に親と繋がりたいという欲求の現れが、“吐き出し”です。
繋がろうとしている動きの始まり、この“吐き出し”の始まりを見逃さないで下さい。
ひきこもっている子どもは、自分がどうしたいかよりも、常に他人を優先し、ずっと良い子を演じてきています。“吐き出し”が始まることは、その良い子から外れていく姿なのです。
子どもは、“吐き出す”ことによって何をしようとしているのか。それは、自分の価値(自分はここに居ていいのか、生きている意味があるのかなど)を確認しようとしているのです。
“吐き出し”の最初は、凄く小さな変化なのです。だから、親は感度を上げていくことが大事なのです。
支援団体、カウンセラー、親の会などは、感度を上げるための道具です。
ひきこもっている子どもは、その道具を使えないので、良い道具をどう選ぶかは親にかかっています。
2.退行
退行とは、心理的危機に陥った時に、発達段階の前段階に戻り、対応しようとする心理的働きで、無意識のうちに起きるものです。お父さん、お母さん、もっと私に関心を向けて下さい、子どもに戻って、もう一度お父さんお母さんの子どもでやり直したい状態の事です。決して、親が退行しておいでよと言うものではありません。子どもの方から親を相手に起こることが重要です。
ひきこもりでない人は、普段から退行を上手く使っています。
ひきこもりの人は、自分の気持ちよりも周りの人の気持ちを優先させてきたために、退行を使えなかった、または使わないできた人が多いのです。それが、家庭が安全な状態になると、これまで経験が無かった退行がワッと出てくるのです。そして、気が済むまで続く退行を使いながら元気になっていくのです。大きな子どもが、母親に寄り添って来ることもあります。それを親がしっかりと意識して引き受けることが大切です。特にお父さんも共に認めてあげることが大事です。
退行で戻る年齢には、お母さんが働き始めた、下の子どもが生まれた、いじめにあった、親と死別した、など何らかの意味があります。そこもしっかりと掴んで下さい。
親が頼りにならないと退行の相手を精神科医やカウンセラーなどに求めて行く場合がありますが、これは危険なことです。何時いなくなるかわからない相手ではなくて、親を相手に起こることが大事です。
3.暴言
子どもが話しかけてきた時に、親は正論「だけどさあ・・・、だってさあ・・・」で応えてしまいがちです。それによって、子どもは親には話が伝わらない、自分の気持ちを分かってもらえないと、段々と口調が強くなって暴言となって行きます。
暴言の裏には、“自分を分かってほしい”、“気持ちを理解してほしい”と言った思いがあり、それを言葉で表現しようとするのです。とにかく分かってほしいと言った“心の叫び”なのです。
そして、その心の叫びの裏には、“このままでいいのか”、”自分はどうなってしまうのか“と言った強い焦りがあります。それに言葉が追いつかなくて上手く伝えられないがために暴言となっているのです。
暴言で何を訴えているんでしょうか、それは“怒り”です。
“怒り”の後ろには、どうしてこうなってしまったのか、自分に対するふがいなさなど、“悲しみ”があります。その“悲しみ”が、形を変えたものが“怒り”であり、いっぱい抱えた“悲しみ”に自分のエネルギーを消耗させないために暴言として出てくるのです。
“怒り”に対してではなくて、その後ろを見てあげて下さい。
4.何を回復と考えるのか
何をもって回復と考えるか、そこをしっかりとしておかないと親の対応がぶれてしまいます。
就学・就業を回復と捉えることに否定はしませんが、実際は動き出した後が難しくて、家で支えてくれる親がいるかどうかがで大きく変わって来ます。
自分が自分でいいと思え、他者からもそう思われていると感じられ、本人が幸せだと感じられる状態が回復だと考えます。社会からどう見られているのかではなくて、本人がどう思うかが一番大事です。
安心安全な環境の中で、自分の中の生きる本能(本当に自分はどうしたいのか)が立ち上がって来ます、それを元に動いてくると喜怒哀楽が正直に機能してくるようになります。あくまで変化の主体は本人です。
自立(自分だけで物事を行う、誰にも頼らない)ではなく、自律(自分をコントロールする、必要な時に必要な人や物に依存できる力を持つ)を目指して下さい。
吐き出し、退行、暴言が出てきたらチャンスです、一つ一つ丁寧に焦らずにぶれないで対応して下さい。
その後で、本日のテーマを含め色々の質疑にアドバイスをいただきました。
グループ別の話し合いを含め概略こんな学習をしました。今回は、年代別のグループとしました。
3月例会のお知らせ
日時 :令和2年 3月8日(日) 13:15 ~ 16:30 (受付 13:00~)
会場 :静岡県男女共同参画センター「あざれあ」5F 502号室
<連続学習会テーマ>『親の取り組みと回復サイン!! 微熱・太る・長時間睡眠・高熱』
講師:SCSカウンセリング研究所 代表理事 桝田 宏子氏
※事前の参加申し込みは必要ありません、当日会場へお越し下さい。
<参加費>1家族 ワンコイン! 500円、 初参加の方、当事者の方 無料
尚、当日10時より準備会を同場所で行っています。会報の発送作業や家族同士の歓談などを行っています。家族、当事者の方など、どなたでも参加できます。むしろ、来ていただく方が多いほうが準備の都合上助かります。例会時とは一味違った雰囲気で、気楽なお話もできます。
また、居場所として活用するのもひとつの方法です。是非、皆さんのご参加をお待ちしています。
3月例会の 受付当番(輪番制)は静岡市駿河区、清水区の方です。よろしくお願いします。
公開講演会のお知らせ
~親亡き後を生きるために~ ファイナンシャルプランナー 畠中 雅子 氏が語る【8050問題】に備える サバイバルプラン
日 時 2月29日(土)13時30分~16時30分(受付13時より)
会 場 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」5F 501号室
参加費 無料
今回は事前の申込をお願いしています。会員の方も必ず早めに申込み下さい。
ピアサポーター養成研修に参加して(その3) (鈴木雅子)
(KHJ本部主催の研修講座 2019年9月8日~9日開催に参加しました)
自立支援医療制度
精神科医療について医療費の自己負担額を軽減する公的制度です。本人に収入がなかったり、低所得の場合、精神科通院に限り、自立支援医療制度を受けられます。通院時の診察と投薬の自己負担額が1割になります。通院者なら容易に取得できるので、医師に相談してみましょう。申請に必要な書類は精神科医療機関か市役所にあります。デイケアもOK。精神科はちょっと抵抗があるという方もいらっしゃるでしょうが、私のように背に腹は代えられないという者もいます。
投稿をいただきました(会員Hさんから)
「たったの一言が 人の心を傷つける。たったの一言が 人の心を暖める」
1つのことばで けんかして 1つのことばで 仲なおり
1つのことばで おじぎして 1つのことばで なかされた
1つのことばは ひとつの心をもっている
わが家にある、お寺から頂いた日めくりの今日の言葉でした。
「なるほど そうだね~」今まで生きてきた中で大いに思い当たる節がある。
「あの時のあの一言が余分だった」「あの時にあの一言を言っておけばよかった」
「子どもにもあの時にこう言えばよかったね」「あの一言が余分だったのだ」
家族との関係、友人との関係、職場での関係、お客さんとの関係 色々と思い当たる。
12月の例会では、門田さんにお話をいただいたが、自分の過去の「嫌だった部分」をあえて人の前で話せるという勇気に大変な感動を覚えた。立派でした。
その話の中で、見知らぬ老夫婦に道を聞かれて、スマホで検索して伝えたら「ありがとう」とひとこと言われた。「自分でもお役に立てたのだ」「自分にもこんなこと言ってくれる人がいるのだ」と感じて、その後の大きなキッカケになったと話してくれました。
日頃から「感謝の心」「よろこびの心」「嬉しいという心」などをもって生活していたら、咄嗟の時に、相手の心につながることばが出せるのかもしれない。あらためて心に刻みたいと思った。
「いっぷくサロン」 気軽にお出かけください(当番がいます)
オープン:毎週火・木曜日 午後1時~4時(但し、祝日、年末年始は除く)
場所 :静岡市葵区一番町50番地 静岡市番町市民活動センター2F KHJ静岡県いっぷく会 事務所内
《会長コラム》
1月13日高校サッカー決勝戦。未だ興奮冷めやらぬ静岡学園の優勝でありました。珍しく全ての試合をTV中継で観戦し、無失点で勝ち進んだ静学の強さに驚いたものですが、それだけに互角の戦いとなった青森山田の巧さがひときわ印象に残りました。今年度は女子の藤枝順心を含め何と6つサッカーの優勝を静岡県勢が獲得したとのことです。サッカー王国静岡の看板が降りて久しい。王国復活を期待するとともに、清水エスパルスにもJ1上位に名を連ねて欲しいものです。それにしても静岡学園優勝パレードがあっても良いのではと思うのは私一人ではありますまい。暗い情け無いニュースが溢れる中、年初景気づけにはもってこいの案件でありますのに。
初めてご参加の方、初回は体験として無料です。その後よろしければいつでも入会手続きができます。年会費は6000円で、出席した時には参加費のご負担をお願いします。
その他、いっぷく会へのお問い合わせは事務局までお願いします。
事務局 電話・FAX 054-245-0766 担当 中津川
E-mail:ippuku-kai@outlook.jp